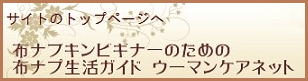布ナプキンのモト、コットン栽培に挑戦
◆コットンの種をまく
布ナプキンのモトである綿(わた)を育ててみたいと思いベランダ栽培に挑戦しました。

これがコットンの種です。
白い方は和棉(わわた)、ブラウンの方はカラーコットンです。
種はほわほわのワタにくるまれています。
コットンの種は綿毛に包まれていて水を吸いにくいので、
種まきの前日から水に浸しておきました。
水で濡らしたキッチンペーパーで種を挟み吸水させました。
いざ、種まきです。
人さし指の第2関節あたりまでの穴を5か所あけて一粒ずつまきました。
(クリップの目印がある方が和棉の鉢です)

まだ殻が付いています。

和棉は5粒の種をまいて全部発芽、カラーコットンは5粒まいて4つ発芽しました。

それぞれの鉢に5粒の種、合計10粒の種をまいて9粒が発芽しました。
その中から、一鉢一本で育てるため一番元気の良さそうなコットンを
一本だけ残して間引きをしました。 ちょっとかわいそうな気もしますが大事に育てます。

支柱と茎を結んでいるヒモはコットンのネル生地です。

手作り布ナプキンのハギレを使いました。
(ビニールヒモじゃかわいそうな気がしてネ)

摘芯を行うと枝が横に張りコットンの実がたくさんなるとのことです。

一番先端の部分を摘み取ります。
私はベランダでの鉢植え栽培なのであまり背丈が伸びたら育てにくいと思い、
摘芯しましたが必ずしも摘芯しなくても良いそうです。
この後1メートル位まで伸び、しばらくして支柱を長いものに交換するほど成長しました。

摘芯してから数日、今まで上に伸びていたのが横に伸びて枝を広げていき、
つぼみがチラホラ付き始めました。
摘芯後は気温も高くなってきたこともあり、
ほぼ毎日鉢底から水が出るくらいの量の水やりをしました。

コットンの花は一日しか咲きません。
早朝に咲き始めて昼前には大きく開花し、夕方にはもうしぼんでしまいます。
コットンの花はなかなか見ることができない貴重な花なのです。
自分で育てているからこそ見ることができる花です。


私はその咲き終わった花の色が赤く変化したのを見て、受粉成功と思っていました。
ところが数日後、鉢の周りに咲き終わった花が数個ポトリポトリと落ちていたのです。

そこで、綿棒を使って受粉をさせることにしました。
お昼前後の花が大きく開いた頃を見計らって、
おしべとめしべの周りをぐるりと軽く綿棒でなでるようにしました。

これがコットンボールです。その形からモモ(桃に似ている)とも呼ぶそうです。
私はそれまで、ふわふわのコットンがはじけたドライフラワーで売られているものを、
コットンボールと言うのだと思っていましたが、
実際は、このまるい実のことをコットンボールと言うのだと栽培して初めて知りました。

この棉の実(コットンボール)がはじけた様子は「棉吹く」と言い秋の季語です。
日本では昔はたくさんコットンが栽培されていて身近な植物だったそうです。
こちらはブラウンのカラーコットンです。

そこで、ワタが雨に濡れないように対策をしました。

キッチンラップを傘にしてワタにかぶせました。
茎にラップ巻き付けただけの簡単な処置ですが
なんとかしのいでくれました。
鉢植えのまま枯れるのを待って収穫することもあるそうですが、
今回はコットンボールが開ききった時点で収穫し、室内で乾燥させます。

秋に収穫し、室内で乾燥させていたコットンから種を取り出したのは年明けでした。
白い和棉は3つの部屋に分かれていて、その一つ一つは繭(まゆ)のようです。
一つのまゆにだいたい5粒から7粒くらいの種が入っていました。

種のまわりにびっしりとワタが密着しているので
種を取り出すのは結構な力が必要です。
種からワタ(棉)を引きはがすという感じでした。
これが自分で育てたふわふわのワタです。
ここから「棉」が「綿」へと変わります。
種を取る前は棉、種を取り加工すると綿という字に変わるそうです。

木になっていると植物、糸へんが付いた後は様々な加工品へ
姿を変えるという、コットンの用途の広さ奥深さを感じますね。

はじめてのコットン栽培で、しかもベランダでの植木鉢による栽培でも
なんとかコットンを育て収穫することができました。
この本を参考にしながらコットン栽培に挑戦しました。
130ページのイラストや写真が適度にある本で読みやすかったです。
綿に関するコラムあり興味深いものでした。


はじめての綿づくり
肥料は和棉もカラーコットンもどちらも与えていません。
栽培中のトラブルに関しては、和棉は虫の被害もなく収穫まで順調でした。
一方、ブラウンのカラーコットンには草丈はよく伸びるものの、
あまり横に枝葉を広げず、アブラムシもたくさん付いてしまいました。
アブラムシにはその都度、ベニカマイルドというスプレー剤で難を乗り超えましたが、
花の咲き方、実の付き方、ワタの様子どれをとっても和棉の方が優っていました。
かつてコットンは、日本中で栽培されていた身近な植物ということですが、
私のような環境で初心者でも栽培できたことから考えてみても、
育てやすい植物だと言えると思います。
ガーデニングの色どりになるような華やかな植物ではありませんが、
成長・開花・結実・棉吹いていく様子と順々に見ることができて、
(一日しか咲かない貴重なコットンの花も間近で見ました!)
布ナプキンのモトになるコットンの栽培は、私にとって大変楽しい経験でした。
◆コットン栽培の関連リンク

これがコットンの種です。
白い方は和棉(わわた)、ブラウンの方はカラーコットンです。
種はほわほわのワタにくるまれています。
◆種まきの下準備
ゴールデンウィークが終わって晴れが続いた頃に種まきをしました。コットンの種は綿毛に包まれていて水を吸いにくいので、
種まきの前日から水に浸しておきました。
水で濡らしたキッチンペーパーで種を挟み吸水させました。
 |
 |
いざ、種まきです。
人さし指の第2関節あたりまでの穴を5か所あけて一粒ずつまきました。
(クリップの目印がある方が和棉の鉢です)

◆発芽
発芽しました。写真は種まきから5日目のものです。まだ殻が付いています。

和棉は5粒の種をまいて全部発芽、カラーコットンは5粒まいて4つ発芽しました。
 カラーコットン |
 和棉 |
◆この頃の水やり
種まきから発芽までは、土の表面が乾いたら水やりをしました。◆間引き
種まきから3週間の様子です。
それぞれの鉢に5粒の種、合計10粒の種をまいて9粒が発芽しました。
その中から、一鉢一本で育てるため一番元気の良さそうなコットンを
一本だけ残して間引きをしました。 ちょっとかわいそうな気もしますが大事に育てます。
支柱を立てる
種まきから30日後支柱を立てました。
支柱と茎を結んでいるヒモはコットンのネル生地です。

手作り布ナプキンのハギレを使いました。
(ビニールヒモじゃかわいそうな気がしてネ)
◆コットンの葉のかたち
これがコットンの葉です。ちょっと葵や楓に似ていますね。
◆摘芯
50センチから60センチくらいになったところで摘芯しました。摘芯を行うと枝が横に張りコットンの実がたくさんなるとのことです。

一番先端の部分を摘み取ります。
私はベランダでの鉢植え栽培なのであまり背丈が伸びたら育てにくいと思い、
摘芯しましたが必ずしも摘芯しなくても良いそうです。
この後1メートル位まで伸び、しばらくして支柱を長いものに交換するほど成長しました。
◆つぼみ
これがコットンのつぼみです。中央にチョコっと黄色いつぼみが見えています。
摘芯してから数日、今まで上に伸びていたのが横に伸びて枝を広げていき、
つぼみがチラホラ付き始めました。
◆この頃の水やり
摘芯までは土の表面が乾き鉢を持ってみて、軽い感じがしたら水やりをしていましたが摘芯後は気温も高くなってきたこともあり、
ほぼ毎日鉢底から水が出るくらいの量の水やりをしました。
◆開花
種まきから46日目、最初の一輪が咲きました!
コットンの花は一日しか咲きません。
早朝に咲き始めて昼前には大きく開花し、夕方にはもうしぼんでしまいます。
コットンの花はなかなか見ることができない貴重な花なのです。
自分で育てているからこそ見ることができる花です。

◆受粉
花が咲いて受粉すると花の色が赤っぽく変わります。
私はその咲き終わった花の色が赤く変化したのを見て、受粉成功と思っていました。
ところが数日後、鉢の周りに咲き終わった花が数個ポトリポトリと落ちていたのです。

そこで、綿棒を使って受粉をさせることにしました。
お昼前後の花が大きく開いた頃を見計らって、
おしべとめしべの周りをぐるりと軽く綿棒でなでるようにしました。

◆コットンの実、コットンボール
受粉に成功した花が枯れると下にまるく実を付け始めます。これがコットンボールです。その形からモモ(桃に似ている)とも呼ぶそうです。
 1.できたてのコットンボール |
 2.少し大きくなり始めたところ |
 3.少し重量感が出てきた頃 |
 4.丸々とし重みも感じるようになった |
コットンボールと言うのだと思っていましたが、
実際は、このまるい実のことをコットンボールと言うのだと栽培して初めて知りました。
◆この頃のみずやり
真夏の暑さと開花・結実を繰り返す日々なので、毎朝たっぷりと水やりをしました。◆ついに白いわたが!
種まきから約3カ月、ついにワタがあふれ出しました。
この棉の実(コットンボール)がはじけた様子は「棉吹く」と言い秋の季語です。
日本では昔はたくさんコットンが栽培されていて身近な植物だったそうです。
 |
殻が少し開いた時の様子 |
こちらはブラウンのカラーコットンです。

◆台風から守る
収穫を目前にして台風が来ました。そこで、ワタが雨に濡れないように対策をしました。

キッチンラップを傘にしてワタにかぶせました。
茎にラップ巻き付けただけの簡単な処置ですが
なんとかしのいでくれました。
◆コットン収穫
台風も乗り越えて自分で育てたコットンを収穫することができました。鉢植えのまま枯れるのを待って収穫することもあるそうですが、
今回はコットンボールが開ききった時点で収穫し、室内で乾燥させます。

秋に収穫し、室内で乾燥させていたコットンから種を取り出したのは年明けでした。
白い和棉は3つの部屋に分かれていて、その一つ一つは繭(まゆ)のようです。
一つのまゆにだいたい5粒から7粒くらいの種が入っていました。

種のまわりにびっしりとワタが密着しているので
種を取り出すのは結構な力が必要です。
種からワタ(棉)を引きはがすという感じでした。
これが自分で育てたふわふわのワタです。
ここから「棉」が「綿」へと変わります。
種を取る前は棉、種を取り加工すると綿という字に変わるそうです。

木になっていると植物、糸へんが付いた後は様々な加工品へ
姿を変えるという、コットンの用途の広さ奥深さを感じますね。
◆コットン栽培の感想

はじめてのコットン栽培で、しかもベランダでの植木鉢による栽培でも
なんとかコットンを育て収穫することができました。
この本を参考にしながらコットン栽培に挑戦しました。
130ページのイラストや写真が適度にある本で読みやすかったです。
綿に関するコラムあり興味深いものでした。

はじめての綿づくり
肥料は和棉もカラーコットンもどちらも与えていません。
栽培中のトラブルに関しては、和棉は虫の被害もなく収穫まで順調でした。
一方、ブラウンのカラーコットンには草丈はよく伸びるものの、
あまり横に枝葉を広げず、アブラムシもたくさん付いてしまいました。
アブラムシにはその都度、ベニカマイルドというスプレー剤で難を乗り超えましたが、
花の咲き方、実の付き方、ワタの様子どれをとっても和棉の方が優っていました。
かつてコットンは、日本中で栽培されていた身近な植物ということですが、
私のような環境で初心者でも栽培できたことから考えてみても、
育てやすい植物だと言えると思います。
ガーデニングの色どりになるような華やかな植物ではありませんが、
成長・開花・結実・棉吹いていく様子と順々に見ることができて、
(一日しか咲かない貴重なコットンの花も間近で見ました!)
布ナプキンのモトになるコットンの栽培は、私にとって大変楽しい経験でした。
◆コットン栽培の関連リンク
informationサイト情報
布ナプキンビギナーのための
布ナプ生活ガイド
ウーマンケアネット

・仕事のご依頼はこちらをご覧下さい
works/活動内容について
・Blog
生理用品と古書の雑記
・web
むかしの女性はどうしてた?
女性雑誌の生理用品広告集
nunonapu.chu.jp/naolog

連絡先
nunonapuchu@yahoo.co.jp
生理用品連絡協議会ができました。
発起人メンバーは『生理用品の社会史』
田中ひかるさんと当サイト管理人です。
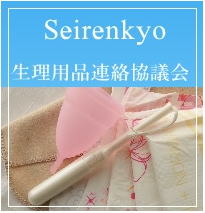
サイトマップ